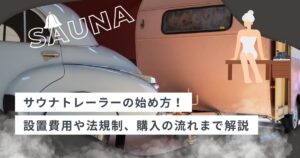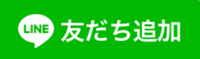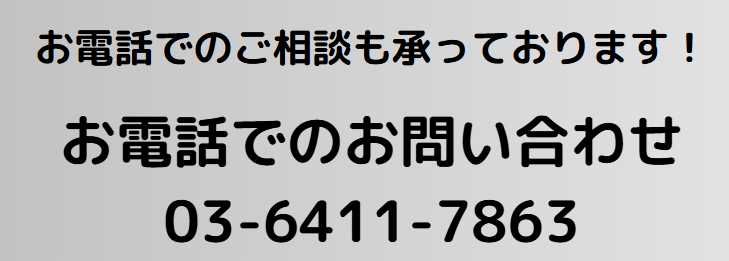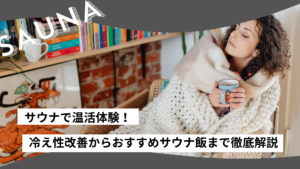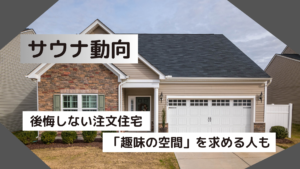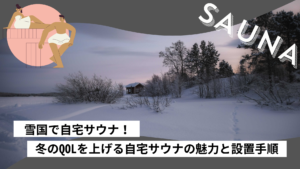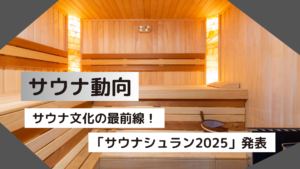大自然の中でととのう!「軽トラサウナ」の自作ガイド!

サウナ愛好家の間で、今注目を集めている「軽トラサウナ」。これは、軽トラックの荷台にサウナ小屋を積載した、まさに「動く秘密基地」です。自宅の庭だけでなく、好きな場所で誰にも邪魔されず、最高に自由なサウナ体験を実現できる軽トラサウナは自作が可能です。
今回は、この軽トラサウナの奥深い魅力と、自作で失敗しないための重要ポイントを解説します。
自作可能な「軽トラサウナ」の魅力とは?

「軽トラサウナ」とは、その名の通り、軽トラックの荷台にサウナ小屋を積載した移動式サウナのことです。
「サウナカー」の一種ですが、特に軽トラックを利用することで、小回りが利き、維持費が安く、日本の狭い道やキャンプ場でも扱いやすいのが特徴です。最近では移動できるプライベートなサウナとして人気が高まっています。
軽トラサウナの魅力は以下の3点です。
天然の水風呂&大自然の中での外気浴
軽トラサウナの最大の醍醐味は、自然そのものを水風呂や外気浴に活用できることです。
そもそも、軽トラックは車体が小さいため、大きなキャンピングカーでは入れないような渓流のそばや林道の奥などに入っていくことができます。そんな大自然に囲まれた場所での外気浴は、森の匂い、潮風、川の音など、五感で自然を楽しむことができます。
また、サウナ後のクールダウンは清流や湖へ入ったり、冬なら雪山へダイブすることも。冷却機で冷やされた水道水とは全く違う、まろやかな天然水の肌触りは格別です。
準備・片付けが不要
アウトドアサウナには「テントサウナ」もありますが、軽トラサウナには圧倒的な手軽さがあります。
まず、テントサウナの場合は現地でサウナテントを広げ、ペグを打ち、ストーブを設置するのに30分〜1時間かかります。雨の日の撤収は泥だらけになり大変です。
一方、軽トラサウナは箱が完成しているので、現地に着いたら駐車して薪に火をつけるだけでサウナが楽しめます。撤収も火を消して扉を閉めるだけです。
「狭さ」が生む極上の熱体験
「軽トラの荷台なんて狭くない?」と思われるかもしれませんが、サウナにおいてはこの狭さが逆にメリットになります。空間がコンパクトなため、薪ストーブに火を入れると驚くほどの速さで室温が上がります。冬場でも100〜110℃の高温サウナを容易に作ることができます。ロウリュを行う際には、サウナストーンに水をかけた瞬間、蒸気の熱波が瞬時に全身を包み込みます。天井が低いため、熱が逃げずに効率よく体を温めてくれます。
また、多くの軽トラサウナは薪ストーブを使います。パチパチという薪が爆ぜる音、揺れる炎を間近で見ながら汗をかく時間は、電気ストーブでは味わえない瞑想的な時間となります。

軽トラサウナ 自作の手順

軽トラサウナの自作は、単なるDIYではなく「重量制限(350kg)との戦い」です。
法的にはサウナ小屋は「荷物」として扱うため、車体に改造を加えず、積んで、固定して、降ろせる箱を作る必要があります。
一般的な製作手順を、最重要ポイントを交えて5つのステップで解説します。
作り始める前に、設計図と重さの計算をします。この手順を怠ると、完成後に車検に通らない(過積載)か、走行中に危険が生じるため、一番重要な手順となります。設計図は使用する部材、重量、換気経路、安全距離などを詳細に計画しましょう。
- サイズ:軽トラの荷台(約1.9m × 1.4m)に収まるサイズです。高さは地面から2.5m以内(小屋単体ではなく地面からの総高)に収めましょう。
- 構造:床・壁・天井を地面で別々に作り、最後に荷台の上で組み立てる「パネル工法」がおすすめです。軽量化しやすく、メンテナンスもしやすい方式です。
- 重量シミュレーション:木材1本、ビス1本の重さまで計算に入れるつもりでシミュレーションを行いましょう。「総重量350kg」には、小屋本体+ストーブ+サウナ石+燃料(薪)+乗員(運転手たち)以外の重量も含まれるため、実質、小屋は200〜250kgで作るのが理想です。
材料はホームセンターで揃えることができます。軽さを最優先に選びましょう。
- 骨組み:2×4材(ツーバイフォー)は重すぎるため、30mm×40mm程度の垂木(たるき)や、軽量な合板を使用しましょう。
- 断熱材:スタイロフォーム(発泡プラスチック系)やグラスウールなどの断熱材は熱を逃がさないために必須です。
- 内装:杉やヒノキの羽目板(薄いもの)は香りが良く、調湿効果があります。
- 外装:ガルバリウム波板(軽くて雨に強い)や、焼き杉(雰囲気は良いが重くなるので注意)などがおすすめです。
- ストーブ:本体だけでなくサウナストーンの重さ(約20〜30kg)も含めた総重量を計算し、過積載にならないよう注意が必要です。
また、走行中の転倒や石の飛散を防ぐため、ストーブを床にボルト固定し、石は蓋をするなど飛散防止の対策が必須です。ロウリュによる錆びを防ぐため、材質はステンレス製を選ぶことが基本となります。
車体に直接打ち付けるのは違法(改造車扱い)になるため、独立した箱を作ります。
- ベースを作る:荷台に載せるための土台を作ります。湿気対策のため、荷台との間にすのこやゴムマットを挟む工夫が必要です。
- 骨組み:垂木で枠組みを作ります。
- 煙突の穴:壁か天井に、煙突を通すための「メガネ石」や「フラッシング(貫通金具)」を取り付ける枠を確保しておきます。
- 断熱:骨組みの間に断熱材を隙間なく埋め込みます。
- 遮熱(防火):ストーブを置く周囲の壁には、ケイカル板(ケイ酸カルシウム板)やステンレス板を貼り、熱で木が燃えないように厳重に対策します。ここは命に関わるので手抜き厳禁です。
- 内装・外装:板を貼っていきます。軽量化のため、見えない部分の板を省くなどの工夫も有効です。
- ベンチ:中に座るためのベンチを作ります。収納兼ベンチにすると便利です。
完成した小屋を軽トラックに載せます。
小屋はボルトや溶接で車体に固定すると「荷物」ではなくなり、構造変更の手続きが必要になるため、「工具を使わずに手で取り外せる(蝶ネジなど)」または「ベルト固定」にするのが一般的です。
- 積載:大人数人、またはジャッキやチェーンブロックを使って慎重に載せます。
- 固定:ラッシングベルト(荷締めベルト)やターンバックルを使い、車体のフックと小屋を強固に固定します。
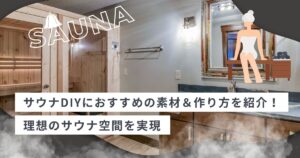
軽トラサウナを自作する際の注意点

軽トラサウナの自作には、安全性と法令遵守に特に注意が必要です。軽トラサウナを自作する際の注意すべきポイントは以下の通りです。
構造・シェルター
- 素材の選定:荷台に設置するサウナ室のフレームや壁には、断熱性と耐熱性を考慮した木材(特に湿気に強いものが望ましい)を使用するのが一般的です。
- 断熱:軽トラックはもともと断熱構造ではないため、壁、床、天井にしっかりと断熱材を組み込む必要があります。
- 換気:高温になるサウナ室にとって換気口の設置は非常に重要です。新鮮な空気を取り入れ、熱気を排出する構造が必要です。
加熱装置(ストーブ)
- ストーブの種類
薪ストーブは火力や雰囲気は良いですが、排煙と防火対策が必須で、取り扱いが最も難しい種類です。
一方、電気ストーブは比較的安全で温度管理がしやすいですが、電源(バッテリーまたは発電機)の確保が必要です。
- 設置
ストーブの周囲は必ず不燃材で囲み、ストーブ本体と壁・床との間に安全距離を設ける必要があります。
- 煙突(薪ストーブの場合)
煙突は高温になるため、車体の金属部やサウナ室の木材に接触しないよう、適切な断熱処理(遮熱板、断熱二重煙突など)を行う必要があります。
法令上の注意点
- 公道走行
サウナ室を荷台に載せて公道を走行する場合、それが「積載物」の範囲内である必要があります。軽自動車の積載制限(長さ、幅、高さ)を超えないように注意が必要です。超える場合は、構造変更の届け出や、そもそも軽自動車の範疇を超えてしまう可能性があります。
- 火気の使用
走行中は、ストーブの使用は厳禁です。駐車場所によっては、火気の使用が禁止されている場所があるため、利用前に確認が必要です。
- 保安基準
走行時に落下・飛散しないよう、サウナ室が荷台に確実かつ強固に固定されている必要があります。
まとめ:自作・軽トラサウナに最も重要な安全性と法令遵守

自作可能な軽トラサウナは、「大自然の中でのととのい」という究極のアウトドアサウナ体験を、手軽に実現できるロマンあふれるサウナです。しかし、その自作は「総重量350kg制限」と「安全性」という二つの大きな課題との戦いとなります。過積載は道路交通法違反であり、ブレーキ性能の低下など重大な事故に直結します。
特に薪ストーブを扱うサウナ室は、遮熱・断熱・換気計画を誤ると、火災や一酸化炭素中毒といった命に関わる事故につながる危険があります。そのため、設計図の段階でストーブの安全距離や煙突の取り回しについて、薪ストーブ専門業者や建築の専門知識を持つ人に必ず相談することをおすすめします。
軽トラサウナは自作のロマンがありますが、法令を遵守し、安全を最優先に進めることが、長く楽しむための大前提です。